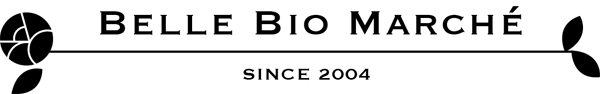冬の養生のはなし ②
こんにちは。ベルヴィスト おうち薬膳UNeのNAHOです。
寒さも一段と増して来ました。
それに新型コロナウイルスの流行もまだこれから未知の状況です。
今年は特に身体を整えて免疫力を上げ、この冬を元気に乗り越えて行きましょう。
食事で「補う」

前回のコラム 冬の養生のはなし① では、冬の邪気の事や「貯蔵」というキーワードをお伝えしましたが、もうひとつのキーワード「補う」事について今回はお伝えします。
前回も書きましたが、冬は身体を養うのに一番良い季節です。栄養を身体に蓄えて滋養し、次の1年間に備えましょう。
それではどのような食材で「補う」か。
薬膳で冬に良く用いるのは、次のような食材です。
元気を補う食材(補気の食材)
穀物類、芋類、鶏肉、牛肉、豆腐、青魚など
「気」は、身体全体に関わるエネルギーです。肉体疲労やストレスなどで消耗します。また気遣いしすぎる人も消耗しやすいです。胃腸の不調がなく、しっかり食べて元気になりたい時にはこのような食材を使いましょう。胃腸が弱い人は消化の良いお粥がおすすめです。
・血を養う食材(養血の食材)
ほうれん草、人参、落花生、イカ、タコなど
女性は毎月の生理もあり慢性的に血が不足している人が多いです。血の生成と流れには気の働きも必要なので、できれば補気の食材と合わせて取りましょう。
・身体を潤す食材(滋陰の食材)
豚肉、貝類、ごま、小松菜、アスパラガス、いちごなど
冬は乾燥し、身体の潤いも不足しやすいです。体内に必要な水分を陰液といいます。これら「滋陰」の食材は身体の陰液を補い臓腑を潤し、また、目、鼻、口、毛髪、皮膚などの乾燥も防ぐ事ができます。
・臓腑を温める食材(温裏の食材)
鮭、鯵、にら、ピーマン、唐辛子、黒砂糖など
「温裏」の裏とは、体内の臓腑を指します。つまり内臓を温める食材です。冬は寒さで冷えやすく身体を温める働きも低下しやすいので、このような食材で冷えを改善しましょう。
・気を巡らせる食材(理気の食材)
玉ねぎ、らっきょう、みかん、グリンピース、ジャスミンなど
冬は寒さで身体がギュッと縮こまりやすくなり、気の流れも悪くなりがちです。気が滞ると血も滞りやすくなります。「理気」の食材には巡りが良くなるよう香りのあるものが多いです。
献立を作ってみましょう

食材を見ていかがでしょうか。
身近にある食材ですよね。
上記の食材で献立を作ってみます。
今の季節美味しい鮭を焼いて、ご飯を炊き、ほうれん草と玉ねぎと人参を入れたお味噌汁、里芋とイカの煮物、小松菜のお浸し、デザートにみかん。
もっと正式にすると生薬をプラスして薬効を高めて薬膳料理を作ったり、お一人お一人の症状に合わせて治療目的で作る薬膳料理もあります。

最近スーパーの中華食材コーナーなどで見かける事もある枸杞の実(クコの実)や松の実、八角、シナモンなどは簡単に手に入る生薬です。
それらを組み合わせて作ってみるのも良いと思います。
例えば上の献立にプラスしたとすると、里芋とイカの煮物に八角とシナモンを一緒に入れて煮る、小松菜のお浸しに松の実を和え、デザートのみかんはカットして枸杞の実をのせてみるのはどうでしょうか。
八角とシナモンの温め作用、松の実と枸杞の実の潤い作用が加わります。
もうこれで立派な薬膳料理です。
こうやって簡単に作れる事を知って皆さんに薬膳を身近に感じてもらえると嬉しいです。少しの工夫でいつもの食卓が皆さんの身体を整えて行くものになりますように。
次回は冬に関係する臓腑について書きたいと思います。