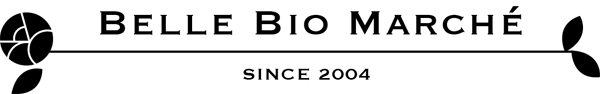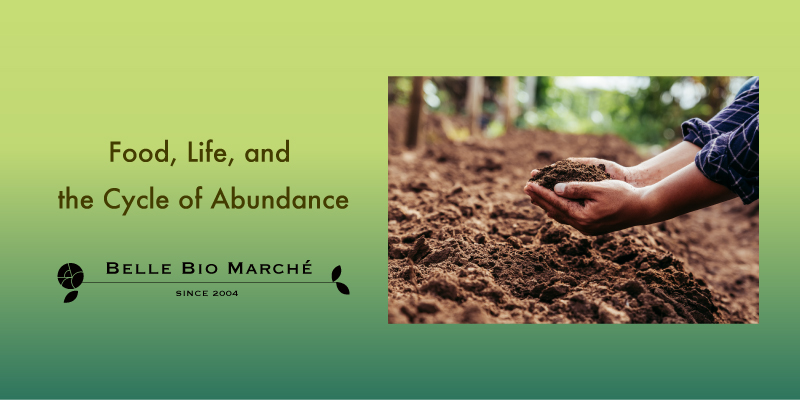
『無駄な草はない』自然栽培の田植え体験レポート|長野県立科町ベルビオファーム
皆さんこんにちは。ベルビオマルシェです。
あっという間に半月ほど経過してしまったのですが、6月の中旬に自然農の農家さんでの作付け体験をさせていただきました。※作付け=田畑に農作物を植え付けて栽培すること
浅間山を臨む美しい田園風景の広がる長野県立科町で農家を営む潮 貴洋さんの田んぼにお邪魔しました。

潮さんのご家族は先祖代々こちらの土地で生活をされていて、お祖父様が畑の手入れをされているのも小さな頃からそばで見ていたそう。
24歳にしてすでに農家として独立されてから3年経っているという経歴をお持ちです。

昨年の10月に弊社が開催したKarina Premium Organics 10th Anniversaryイベントでのマルシェ出店に快くお越しいただき、その際にお持ちいただいた”亀の尾”という品種のお米が素晴らしく美味しく、会員様からもご好評をいただきまして、2025年は会員様へ向けて新米の予約をさせていただきたい!というお話から、ベルビオファームエリアを確保していただき、お米づくりをしていただいております。
秋の収穫後に予約販売を開始するのはコシヒカリの原種と言われる”亀の尾”なのですが、亀の尾の作付けはすでに数日前終えたとのことで、今回はコシヒカリの作付けを体験させていただきました。
「無駄な草はない」自然との共存が生む、豊かな循環のサイクル
自然栽培でのお米づくりは、慣行栽培でのお米づくりとは苗床の作り方からして全然違うそうで、安定した収量を確保するために肥料や農薬を適切に使用する慣行栽培と違い、自然栽培では土の力や植物の力に任せて、農薬や肥料を使わずに土壌の生態系の循環で、作物を育てていきます。
自然栽培(自然農)・・・自然の力を利用した農法。その土地の土壌に棲む微生物の生態系を豊かに育て循環させ、化学肥料や農薬を使用せずに作物の自然の力を活かして作物を育てる。
※現在の日本では有機農法(オーガニック)の農家さんが全体の0.5〜0.6%と言われていて、自然栽培は全農家の0.1〜0.3%程度と言われています。
慣行栽培・・・敗戦後に急速に普及した化学肥料や農薬を使用して、大規模かつ効率的な生産を可能にする栽培方法。
ベルビオマルシェでは、「肌を育てる」化粧品としてオーガニックコスメを推奨しています。肌も常在菌の存在があってこそ美しく健康な状態が保たれるので、まさに自然栽培の土づくりと同じです。
自然栽培の苗は肥料を使わずに自然の力での発育を促すので、慣行栽培の苗よりも苗床にいる期間が長く、少し黄色味がある苗になります。最初から青々とした緑色の強い苗は肥料を使って成長を促した慣行栽培のものだそう。

そして作付けのために、田んぼを整えるところにも自然栽培ならではのポイントが!
潮さんが今回ご案内してくださった田んぼは深水管理といって通常よりも深い水位の田んぼでした。深水管理をすると水温が上がりにくいため、稲の生育はゆっくりになりますが、逆に草の発芽や成長を抑えることができます。水深が浅すぎると、草が勢いよく生えてしまい、稲が負けてしまう(草負け)ことがあるので深水を保つことで、草を抑えつつ稲がしっかり根を張る環境を整えているのとのこと。
要所要所に様々な意味があり、本当に様々な農業に関わる知恵が集約されています。

ここで興味深かったのがタイトルにもさせていただいた潮さんの「無駄な草はないから、雑草っていう表現ができない」という言葉。
自然栽培で一番大切なのが「土壌づくり」そして、土壌づくりの最も重要なメンバーといえば「微生物」。
微生物がいるかいないか、微生物の多様性が維持されているか否か、によって、肥沃な土地というのが決まってきます。
もともとの土地を耕して、微生物が生まれる土壌を人間が育むという自然と人の営みによって、美味しくて生命力の強い作物が作られます。
慣行栽培では農薬を使うので、この土壌の微生物や微生物の多様性はほぼないと言われています。
自然栽培では、微生物が棲みやすい土づくりをするために、あえて一旦自然に任せて草が育つのを見守ります。
微生物は根っこのところにたくさん集まる傾向があるので一旦根を下ろさせることが大切とのこと。興味深いですよね。
「その土地に自生している草は意味があってそこに生えてくる。その土地を豊かに育んでくれるのもその草の存在あってこそ。なので自分は雑草っていう言葉を使いたくないんですよね」とおっしゃっていました。
そして水田に草が生えてから、その草を取り除く「しろかき」という作業があるそうなのですが、通常は1回のところ、潮さんの田んぼでは3回しろかきをして、作付けに備えるとのことでした。
ここでも一手間ならぬ、倍の手間がかかっています。
立科町の土は高粘土でねっとりしているため、稲作に適しているそう。
いよいよ作付け。
4月の半ばくらいから準備してきた苗床を見せていただきました。
逆さまにしても落ちない。根の強さを感じる苗たち。

苗床にも潮さんのこだわりが詰まっていて、根詰まりを起こさないよう標準より目の粗いものを使用しているそう。

コシヒカリの苗。大体1つの苗でお茶碗一杯分とのこと。

苗が機械に絡まらないように丁寧に苗を機械にセットしていきます。

田植え機初体験。ベルビオチーム4名でそれぞれ1往復させていただきました。まっすぐ操作するのが難しい…

毎日食べているお米。小さい頃からお百姓さんに感謝して残さずいただきましょう。と言われていましたが、こうして実際に農家さんを訪れることでさらに感謝の念が生まれました。
ここから定期的に田んぼを訪れて、様子を見ていきたいと思います。
ベルビオファーム亀の尾のお米のご予約開始は、秋頃を予定しております。
微生物たっぷりの田んぼで育てられている、自然の恵みが詰まったお米。ぜひお楽しみに!
今回、作付け体験をさせていただき、真っ直ぐな瞳で自然農にまつわる現状などをお話ししてくださる潮さんにもっと色々お伺いしたいと、インタビューをさせていただきました。
「上手にやれば、慣行栽培と同じだけの収量だって望めるんですよ」と語っていた潮さん。なぜ自然栽培という選択をしたのか?など心に響くストーリーをご紹介いたします。