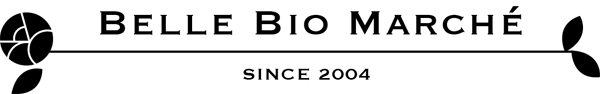「先祖から受け継いだ大切な土地を守りたい」―潮貴洋さん(24歳)が語る、自然栽培への熱い想い[3000字インタビュー]
日本の食料自給率はわずか37%(※2022年農林水産省発表)──。
そんな時代にあって、農薬や化学肥料に頼らず、土地本来の力と微生物の循環を生かして野菜や米を育てる「自然栽培」に取り組む若き農家がいます。
今回ご紹介するのは、長野県立科町で自然栽培に情熱を注ぐ、潮貴洋(うしお たかひろ)さん、24歳。
工場勤務を経て農業の道に戻った潮さんが出会ったのは、宇宙や生命の循環にまでつながる、壮大な「土づくり」の哲学。「この国の土地を守りたい」と語るその真っ直ぐな眼差しからは、次世代の農業への確かなビジョンが伝わってきます。
本インタビューでは、潮さんが自然農に目覚めたきっかけから、土づくりの驚きの工程、慣行農業との違い、立科町での挑戦、そして未来への想いまでを、じっくり伺いました。
自然栽培との出会い 「祖父の背中」と「オーガニックな義母」
自然栽培を始めたきっかけは何だったのでしょうか?
先祖代々、長野県立科町で暮らしていて、小さい頃から祖父が田畑で作業している姿を見て育ちました。農業は常に身近な存在でした。農業高校を卒業後は一度工場に就職したのですが、体質に合わず3ヶ月で退職。その後、現在の妻の母親の勧めで農業にもう一度触れることになりました。
義母はオーガニックな考え方を持っていて、大豆を育てて味噌や醤油を手づくりしていた方でした。その畑で草取りなどをしているうちに、幼い頃の祖父との農業の思い出が蘇り、「やっぱり農業をやりたい」と感じたんです。
その後、様々な農家で修行をさせてもらう中で、ズッキーニを自然栽培している農家さんと出会いました。その方は特に”自然栽培(自然農)”という言葉を使っていたわけではないのですが、無化学肥料・無農薬で栽培されていて、なにより野菜の味がこれまで食べていたものとは全く違っていて、衝撃を受けました。
その体験が、自分もこういう野菜を作りたい、ずっと食べ続けたいという思いにつながり、自然栽培を始めるきっかけになりました。
その方の哲学的な考え方にも影響を受けたそうですね?
はい。畑や地球、宇宙、人間の体内すらも、すべてが一体であるというか。畑の中の微生物は、まるで宇宙に輝く星のような存在で、それらが腸内にも棲みついている。そのつながりを活かすことで、自然の循環が生まれ、いずれまた土に還っていく。
そうした大きな流れや循環の中で、不自然なものを摂取せず、自然の理に沿って生きることが大切だと感じるようになりました。
自然栽培を始めてから、ご自身の身体に変化はありましたか?
もともと特に病気がちというわけではなかったのですが、インフルエンザや流行りの風邪などに家族の中で真っ先にかかるタイプでした。でも自然栽培を始めて、自分の育てた土地の作物を食べるようになってからは、まったく風邪をひかなくなりました。
土づくりの神秘 発酵した菌床は“60度の小さな地球”だった
土づくりについて詳しく教えてください。
自然栽培で最も大切なのが”土づくり”です。僕は4年間の修行を経て独立したのですが、1年目はまず土を整えることから始めました。
具体的には、土の中の悪い成分を吸ってくれる麦やとうもろこしを植え、それらが育った後に上の部分を粉砕し、緑肥として土に混ぜます。さらに、きのこの菌床(培地)をまいて発酵を促すと、数日で発酵熱が出て60℃近くまで温かくなり、まるで小さな地球のような球体ができます。
この発酵の過程で微生物が活発になり、豊かな土が育っていくのです。2年目以降は何も入れず、その土の力と微生物の循環によって作物を育てていきます。


先日作付け体験をさせていただいたのですが、立科町の土はすごくお米作りに適しているそうですね。
そうなんです。この間もお話ししましたが、もともと屋根の瓦などに使われる強粘土の土で、特にうちの田んぼの土は立科町の中でも特に強粘土で、お米の味をしっかり引き出してくれるんです。
蓼科山から流れてくる綺麗な水と、この強粘土の土が美味しいお米作りのベースになっています。

慣行農業と自然農(自然栽培)の大きな違いはどこにあるのでしょうか?
慣行農業では、化学肥料を使って作物を育てます。ただし、肥料の過剰摂取によって植物が栄養を吸収しきれず、余分な成分を放出することで、それが虫を呼び寄せるホルモンとなってしまいます。結果的に虫が増え、農薬を使わざるを得なくなる。だから、化学肥料と農薬はセットになってしまうんです。
一方、自然農では微生物が豊富な土が育っていると虫が寄ってこないので、農薬を使う必要がありません。収量の差がよく問題にされますが、うまくやっている人は、慣行農業と同じくらいの収量を出しているケースもあります。
なぜ多くの農家さんが自然栽培に切り替えないのでしょうか?
単純に「知らないから」だと思います。
自分の祖父も昔は農薬や肥料は使っていなかったのが、日本の農業が変わったのは戦後、敗戦の影響で海外から化学肥料や農薬が一気に入ってきたことが大きいです。当時は生きるのに必死で、とにかく食糧をたくさん作らないといけない状況だった。だから仕方なかったとも思います。
土づくりに時間がかかることも、移行のハードルの一つでしょうか?
そうですね。長年化学肥料や農薬を使ってきた土地を、微生物が棲みやすい環境に戻すには、やはり一度「土をリセットする」必要があります。残留農薬が抜けるまでに3年くらいはかかると言われていて、その間の収穫や収益の見通しが立てにくいことが、切り替えの難しさになっていると思います。
自然農と肌の関係について、私たちの活動と重なるように感じます。
(インタビュアーより) ベルビオマルシェでは「肌を育てる」ことをテーマに、肌本来の力=素肌力を大切にしています。常在菌が活躍する健康な肌の仕組みは、自然農での「微生物が活きる土」とすごく似ていると感じます。
肌もずっといわゆるケミカルコスメを使い続けていた人が、オーガニックコスメに移行すると、好転反応のように肌がガサガサになったりバランスを崩すことがあります。しばらくすれば肌本来の力が復活してくるのですが、そこで耐えられなくて、またケミカルコスメに戻ってしまう人もいます。肌自体が生まれ変わると全然ふっくら感も違ったり、潤いも全然違うのですが…。
(潮さん) それは面白いですね!初めて聞きましたが、確かに似ているかもしれません。
立科町で自然栽培に挑戦する意義
立科町はもともと自然栽培でのお米づくりは許可されていなかったと伺いました。
立科町には長野県にある種籾採取場の2つしかないうちの1つがあるんです。
もし自然栽培をやっていて、病気が出てしまった場合に来年の種に影響が出てしまったら困るのでやめてほしいと最初は言われました。
でも自然栽培でやっていきたかったので、自分なりに色々調べて、周りの農家さんの使っている種のことなど調べて、影響がないだろうと判断して自然農でのお米づくりを進めました。それからは役場から何も言われなくなりましたし、真面目に取り組んでいくことで認めてもらえるようになるんじゃないか?と思っています。
実際に立科町でかなり大きくお米づくりをしている農家さんが、僕の活動を見て去年から自然栽培に切り替えていて、こういった状況を説明したんですが、だったら俺たちで変えていこうよ、と。うちの亀の尾の種も購入して、作ってくれています。
潮さんの信念 「この国の土地を守りたい」その理由
素晴らしいですね!自然農を進めていく上で大事にしている哲学のようなものはありますか?
自分は、この国の土地を守る。という意識を持っています。
今流通している農薬や肥料のほとんどが外国産のもので、もともと日本ではそういったものを使わないで作物の栽培ができていたのが、今は外国産の農薬や肥料が土に撒かれている。
元々の土地が外国に侵略されてしまっているような感覚を持ってしまいます。
先祖が大切に育んできた土地がそういったもので汚染されてしまうというか。
なので自然栽培を進めていくことで、豊かな土壌に戻して、その土地にあった美味しい野菜やお米を私たちが食べて、豊かな循環を取り戻していきたいと考えています。
この先どのようなビジョンを持っていますか?
先ほどの役場との対立とかもそうなんですが、圧倒的に自然栽培のことを知っている人が少ないんですよね。
そもそも自然栽培の存在を知っている人がどこに行っても少ないんです。田んぼ作りもほとんどが慣行栽培で。そもそも昔は自然栽培だったんだよ。っていうのを知っている人がほとんどいないので、自分が積極的に発信していくことで拡がる繋がりがあると思うので、どんどん発信して伝えていって、少しでも変化を起こせたら良いなと思っています。
最近では若い世代が農業を始めたり、興味を持っている人が多いという話も聞きます。
そうなんですよね。結構自分達で畑をスタートして、無肥料、無農薬でやりたい。っていう人がいるんですが、例えば有機肥料と書いてある鶏糞とかでも、じゃあその肥料の元になっている動物が食べている作物はどうなんだろう?とか突き詰めていくことが結構大事で。
あと自然栽培の世界でも、それぞれこだわったやり方を持っている農家さんもいて、そうすると対立とかも生まれたりもするんですよね。でも最終的には自分なりの方法を模索していくことが大事だと思っています。
自然との関わりや循環の中で、人がそこに手を入れて、地球からいただいていくっていうシンプルなこと。
自然農に興味がある方がいれば自分はいつでもオープンに対話をしていきたいと思っているので、興味をお持ちの方がいればぜひ立科町に足を運んでみてください。

こちらの質問にまっすぐに丁寧に答えてくださった潮さん。この国の土地を守っていきたい。という言葉が胸に響きました。
ベルビオマルシェでは引き続き秋の収穫まで、定期的に田んぼを見にいきたいと思います。
潮さんの作ってくださっている美味しい亀の尾のお米は、ご予約制でご注文を承る予定です。
ぜひ楽しみにしていてください。